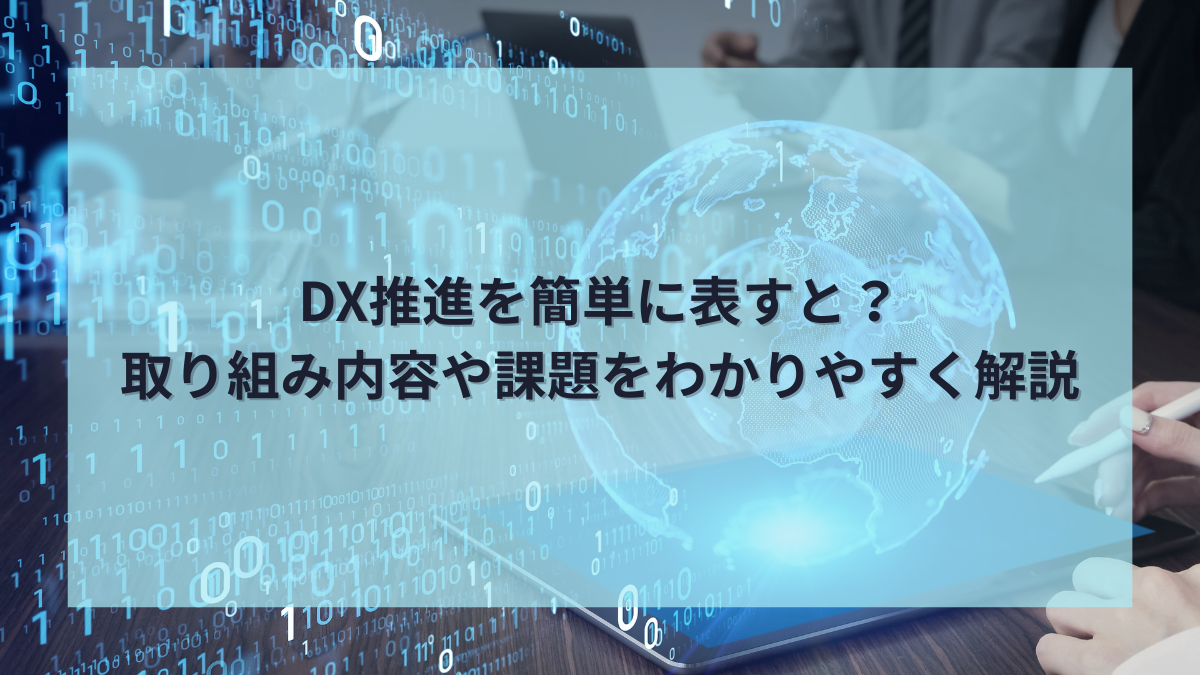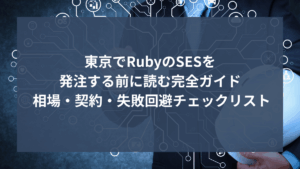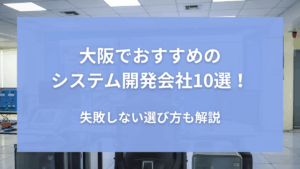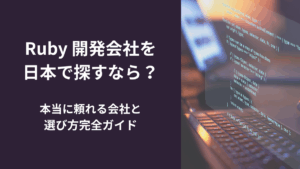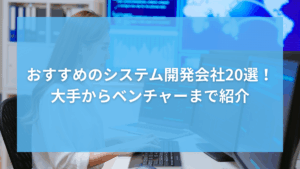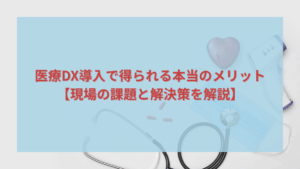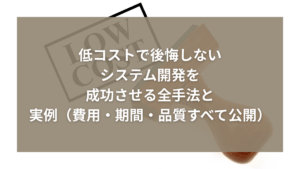「DXを推進したいが、まず何から始めるべき?」
「DXの取り組み内容のイメージが湧かない」
このような悩みを抱えている企業も少なくないはず。ビジネスの現場では「DX推進」が叫ばれているものの、具体的に何に取り組めばよいのか、イメージが掴めない方も多いでしょう。
そこで本記事では、DX推進の概要について次のポイントを中心に解説します。
- DX推進とは何なのか?簡単な解説
- DX推進における取り組み内容
- DX推進に成功した中小企業の事例
この記事を踏まえたうえで、自社に合ったかたちでDXを導入しましょう。
DX推進とは?
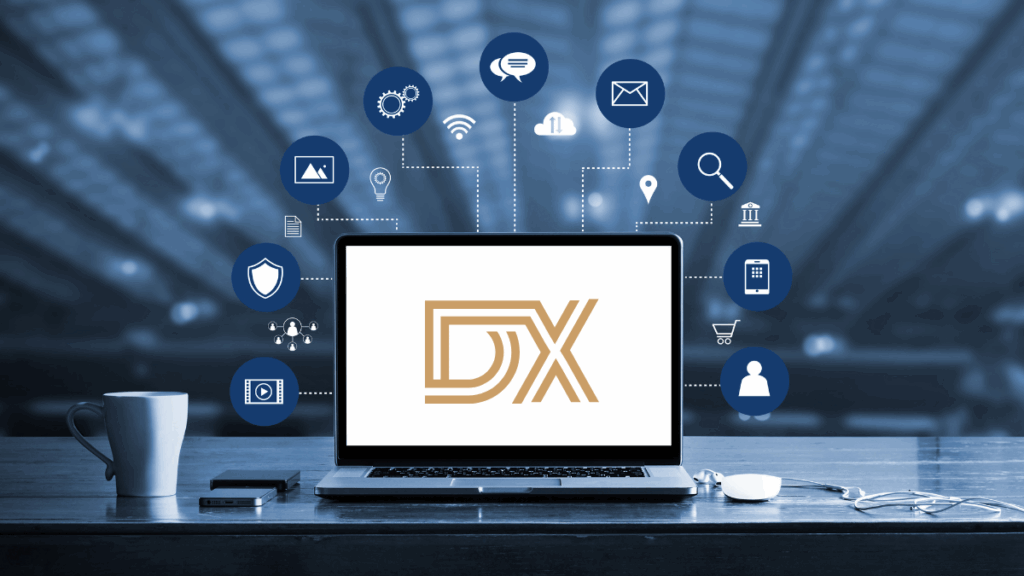
DX推進の前に、まずはDXとは何なのか?です。DXとは、Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)の略語のこと。わかりやすくいえば、デジタル技術の活用によって業務プロセスを効率化することです。
たとえば、クラウドサービスを利用したり、データ分析を行ったりすることで、業務の効率化や顧客満足度の向上を図ります。
DX推進の目的
企業がDXを推進する目的は何なのか。最大の目的は「競争力の強化」です。現代社会では、この10年でスマートフォン利用が当たり前に。国民のほとんどがスマートフォンをもっている、つまり消費者ニーズがめまぐるしく変化する時代になっています。
ビジネスにおける環境変化も激しいため、それに対応するため、「デジタル」や「インターネット」などを活用した仕組みを取り入れる必要があるのです。そうすることで、消費者ニーズをはじめビジネスにおける変化にも順応でき、自社の競争力が高まります。
DX化とIT化の違い
DXと間違えやすい用語に「IT化」があります。どちらもデジタル技術を用いる点において意味は同じです。ただし、もう少し深掘りしていくと、ニュアンスが少し異なります。
| IT化 | 業務効率化や生産性向上、コスト削減が目的 |
|---|---|
| DX化 | ビジネスモデルや組織単位での変化が目的 |
わかりやすくいえば、IT化が狭義、DX化が広義です。デジタル技術を導入して、効率化やコスト削減など、ミクロ的な成果を目指すのがIT化。対して、「デジタル技術によって、企業として大きく変化させたい」、このように考えるのがDX化です。
DX推進における取り組み内容
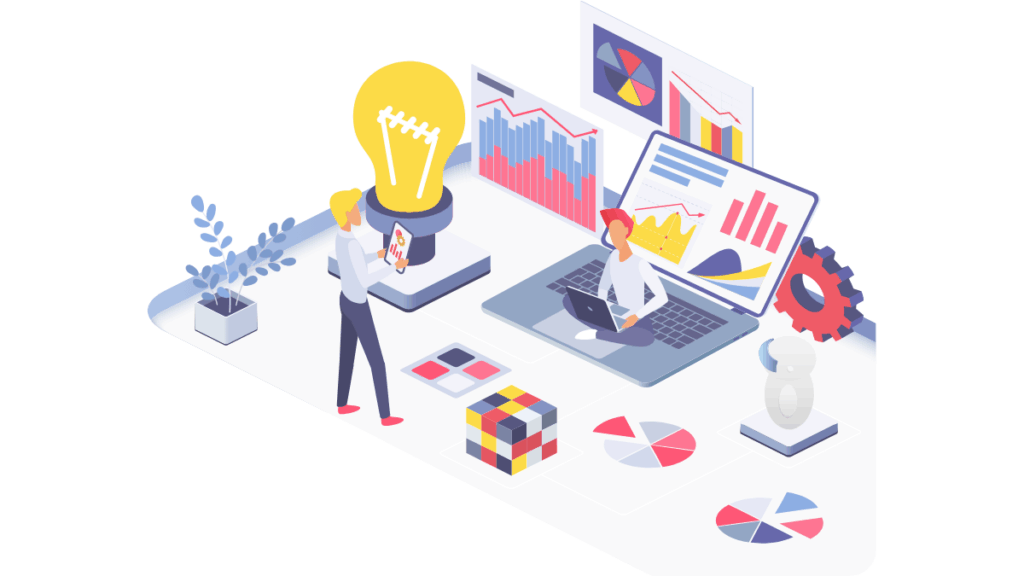
DX推進と聞いても、どのような取り組みをすべきかイメージも湧きにくいかと思います。「何をどうするべき?まずは何をやればいいの?」と疑問をもっている方も多いでしょう。そこで、DX推進でよくあげられる5つの取り組み内容を紹介します。
- コミュニケーションをスマート化させる
- 書類をデジタルに置き換える
- 営業に専用ツールを用いる
- 会計ソフトを導入する
- 多角的にデータ分析を行う
1. コミュニケーションをスマート化させる
社内におけるコミュニケーションの定番といえば、電話やメールですよね。これをDXによってスマート化させます。ChatWork(チャットワーク)やSlack(スラック)と呼ばれるチャットツールの導入。また、Zoom(ズーム)といったオンライン会議ツールを導入するといった方法です。
これらのツールを導入すれば、スマートフォンから簡単にチャットや会議が可能です。グループでのコミュニケーションや会議の予約、タスク管理なども行えます。
2. 書類をデジタルに置き換える
書類をデジタル化させるのも、DX化の代表例です。社内に書類が溜まっていく一方で、うまく保管できていない企業も多いでしょう。取引先や顧客との契約情報、社員の個人情報、などあらゆる情報を扱います。これらを「紙」で管理するのは大きな負担になります。
書類をカテゴリー分けする手間がかかるのはもちろん、保管するスペースも必要です。契約書や顧客台帳などをデジタル化させれば、管理工数を大幅に減らせます。
3. 営業に専用ツールを用いる
専用ツールを用いることで、営業部署のDX化も図れます。どの企業も、営業部署には膨大な情報が溜まるでしょう。アポイント先や追客状況、資料、既存取引先の情報などさまざまです。これらを営業マン自身がオフラインで管理するのは大きな負担となり、コア業務を圧迫します。
そこでおすすめしたいのが、営業支援ツールの導入です。営業に関するあらゆる情報をワンストップで管理できます。またツールによっては、アポイント先の場所をスマホのマップ上に表示させる、日報を提出するといった使い方が可能です。
4. 会計ソフトを導入する
会計ソフトの導入も、DX推進における代表的な取り組みのひとつです。日々の仕訳業務や帳簿作成、経費精算、決算書の作成など、経理部門に求められる業務は膨大なもの。これらをExcelや手書きで行うのも時間がかかります。
会計ソフトを導入することで、スマートな経理が可能に。仕訳や帳簿作成が自動化されるなど、ほとんど手間がかかりません。また、Excelのように「関数に詳しい社員でなければ使えない」といった属人的な課題も解消できます。
5. 多角的にデータ分析を行う
多種多様なデータをさまざまな角度から分析できるのもDX推進の大きなメリット。たとえば、顧客の購入データをもとに趣味嗜好を発見したり、在庫データから需要予測をしたりといった使い方ができます。
データドリブンな意思決定をしていない場合、「なんとなく売れそうだから」「なんとなく顧客から反応が良いから」など、主観的な判断をしがちです。しかしそれでは博打的な経営に判断をする可能性があります。DX化によって客観的なデータを収集・分析することで、より失敗の少ない、最適な意思決定ができるようになるのです。
DX推進のメリット
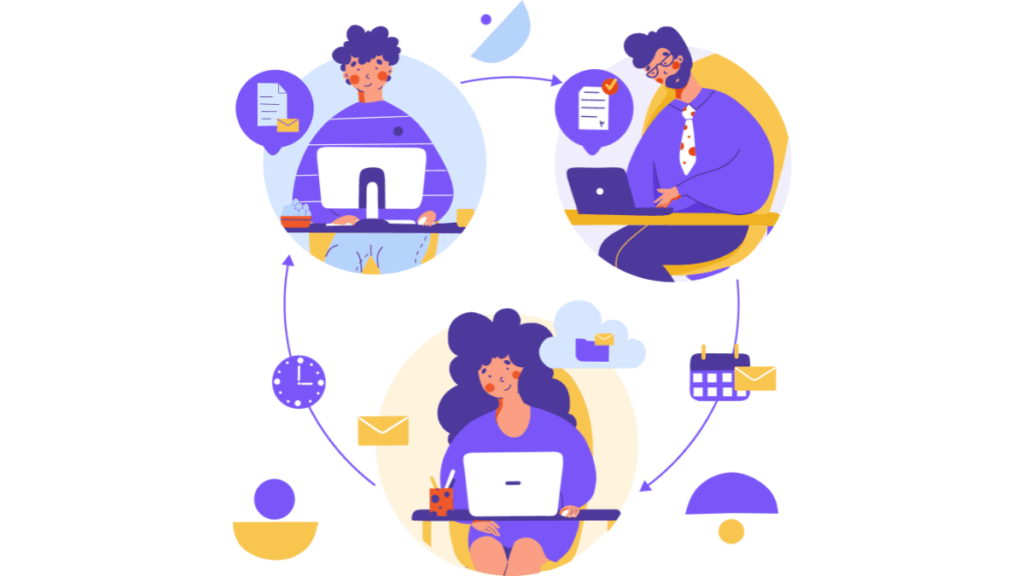
DXを推進することで、オフライン業務よりも多くのメリットを享受できます。代表的なメリットは次のとおりです。
- 人手不足でも生産性を保てる
- 顧客ニーズの変化を掴みやすくなる
- テレワークが捗るようになる
- 他社との競争力が高まる
1. 人手不足でも生産性を保てる
業務のオンライン化、これはDX推進の醍醐味です。さまざまな業務をオンラインで完結できるため、紙やExcelなど従来の方法と比べて生産性が飛躍的に高まります。
人手不足に悩んでいる中小企業も多いはず。人手不足に悩むと、つい「人材採用にコストとリソースを使おう」と考えがちです。しかし、膨大なコストをかけても、優秀な人材を集められるとは限りません。DX化を進めることで、既存メンバーで業務効率を最大化できます。
2. 顧客ニーズの変化を掴みやすくなる
データ分析を行うことで顧客ニーズの変化を掴みやすくなるのも、DX推進の大きなメリットです。たとえば、CRM(顧客管理システム)を導入すれば、顧客の基本データや購買履歴を見える化できます。
データを見ることでニーズや購買意欲の変化がわかり、それに適したアクションを実行可能です。自社の商品・サービスのシェア拡大にもつながるでしょう。
3. テレワークが捗るようになる
DXでは「インターネット」や「デジタル」を駆使するため、テレワークが捗るようになります。たとえば、書類を紙からデジタルに置き換えれば、インターネット上で誰でも閲覧が可能です。見たい書類があるのでオフィスに行かなければならない、といった煩わしさも解消されます。
SFA(営業支援システム)や会計ソフトなどクラウド型のツールも多く、社員はいつでも、どこでも閲覧や編集ができます。ツールではアクセス権限も設定できるため、細かく設定することで十分なセキュリティ対策が可能です。
4.他社との競争力が高まる
DXを推進することで、結果的に他社との競争力が高まります。スマートフォンやインターネットが発達した現代では、めまぐるしく市場が変化しています。顧客ニーズはもちろん、それに合わせて他社の業務指針も変化し続けるため、従来の体制で競争力を維持するのは困難といえるでしょう。
そういった時代の中では、「DXをどのように推進するか」が重要です。自社の組織規模や商材などに応じて必要なITツールを導入し、いち早く分析を行うことで、他社に負けない競争力を獲得できます。
DX推進で企業がぶつかる課題
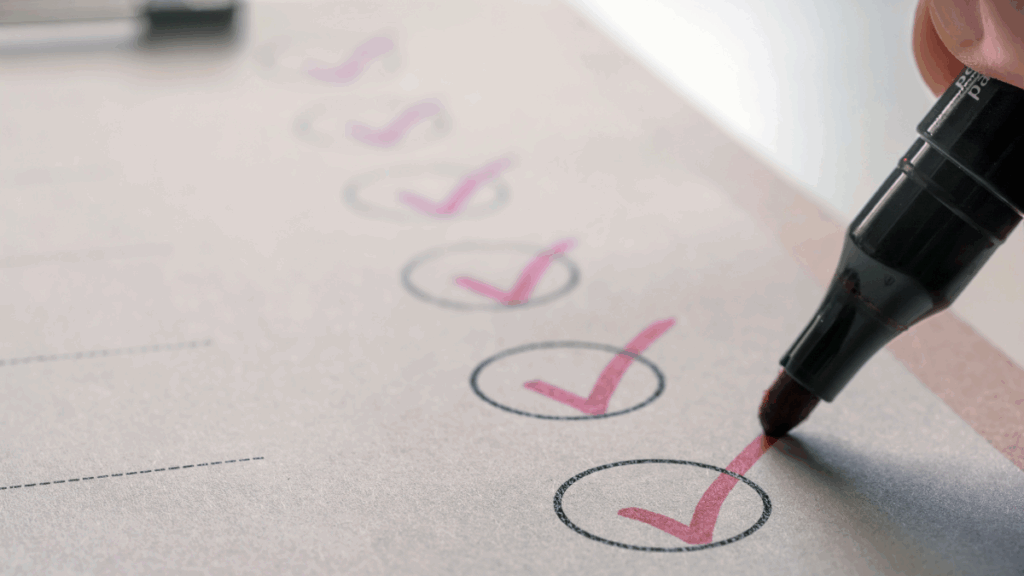
DX推進には多くのメリットがあるものの、導入が必ずうまくいくとは限りません。企業がぶつかる代表的な課題として次のものがあげられます。
- 社内にDX人材がいない
- DX化の予算を確保できない
- セキュリティに懸念がある
1. 社内にDX人材がいない
DX化に成功すれば生産性が高まり、企業に多くの利益をもたらしてくれます。しかしながら、「DXを主導できる人材がいない」といった企業も少なくありません。そもそもデジタルやインターネット、ITツールに明るい社員がいなければDX推進は難しいといえます。
社内にDXチームを設置して、チームで調べながらDXスキルを磨く、または外部に委託するなどの方法でDXを推進する必要があるでしょう。
2. DX化の予算を確保できない
DX推進には一定の予算が必要です。たとえば、会計ソフトを導入する場合、ソフトの初期費用や月額利用料が発生します。個人利用なら安価ですが、企業単位でソフトを利用する場合、数万円〜数十万円のコストがかかります。初期費用や月額利用料、使用量に応じた料金などさまざまです。予算が少なければ、それだけDX化できる幅も狭くなってしまいます。
組織の生産性を飛躍的に高めたい、業界トップのシェアを獲得し続けたい、など高い目標を掲げる場合、DX推進に対して相応のコストをかける必要があるでしょう。
3. セキュリティに懸念がある
DX推進によって業務効率は大幅に高まります。しかし、多くの場合インターネットを利用するため、セキュリティに懸念が残ります。ベンター(ツールの提供企業)側も万全のセキュリティ対策を講じていますが、とはいえインターネットを介して利用するため、情報漏えいのリスクを払拭しきれません。
セキュリティを第一に考える場合は、クラウド型ではなく、システムの運用保守を自前で行える「オンプレミス型」のツールを利用するといった対策が必要です。
DX推進を成功させるためのポイント

DX推進ではある程度の予算やリソースが必要なので、誰しも「失敗したくない」と考えるでしょう。ここでは、DX推進を成功させるためのポイントを解説します。
- DX推進を目的ではなく手段として考える
- ツール導入と同じように人材育成にも注力する
- 大規模ではなくスモールスタートさせる
1. DX推進を目的ではなく手段として考える
企業にとってのDXは、あくまで「手段」であり、目的ではありません。ここが混同すると、解決したかったはずの課題を見失ってしまいます。
ただ単にITツールを導入するだけでなく、「導入して、何を実現したいのか?」まで深く考えることが大切です。そのためには、デジタル戦略と経営戦略の2つを融合させて考える必要があります。
2. ツール導入と同じように人材育成にも注力する
DX推進のよくある課題として、「DX人材がいない」といった状況があげられます。人材がいないのにツールを導入するといった、まさに「DX自体が目的化」すると、こうした課題に直面します。
そのため、ツールを導入する場合は、それを扱える人材や、教育できる人材がいるか確認しましょう。いない場合は、ツールを取り入れる前に、まずは育成に注力する必要があります。
3. 大規模ではなくスモールスタートさせる
DXはスモールスタートさせるのがポイント。DXは革新的なものなので、つい全社的にスタートさせがちです。しかし、社内体制が整っていないままスタートさせると多くの場合、失敗してしまいます。
DXの目的を社内共有したり、ツールの使い方を浸透させたりといった事前準備が必要でしょう。そもそも、セキュリティの社員のデジタルリテラシーも高めなければなりません。
準備を整えないまま全社で導入すると、「DX」という言葉だけが独り歩きし、結局社内に定着しないといった状況になります。これらを防ぐためにも、まずは上層部だけ、特定の部署だけ、などスモールスタートさせることが大切です。
DX推進に成功した中小企業の事例
最後に、DX推進に成功した中小企業の事例を2つ紹介します。
手書き伝票のデジタル化によって業務効率が大幅に向上 | 株式会社ホープン
画像引用:株式会社ホープン
株式会社ホープンは、印刷業を皮切りに、教育関連企業向けのアウトソーシング事業、デジタルコンテンツ作成などを行う会社です。同社のDX推進におけるポイントは次のとおりです。
| 課題 | 手書き」で伝票を作成していたため、人材確保や属人化に課題を感じていた |
|---|---|
| DX推進の内容 | 文書のスキャン読み込み、タブレット注文に移行した |
| 結果 | ヒューマンエラーの削減や属人化の解消につながった |
同社では、これまで手書きで伝票を作成していたため、社員の業務負担はもちろん、新人スタッフに対する教育にも工数がかかっていたそう。そこで「スキャンto PDF」や「AI-OCR」など、文書をスキャンするだけでデータ化できる施策を行いました。
注文もタブレットでの受け付けに変更。その結果、社員の負担が大幅に軽減されました。タブレットに自動計算機能を付帯したことで、ヒューマンエラーもほぼゼロに。「誰がどのような注文を受け、どこに何を記録したかわからない」といった手書き伝票ならではの属人化も解消しました。
参考:デジタル活用・DX事例集 vol.39 株式会社ホープン | 東京商工会議所
補助金でコストを軽減しながらDX人材を育成 | 株式会社SND
画像引用:株式会社SND
株式会社SNDは、ダイヤモンド工具の製造や販売を行う会社です。同社のDX推進におけるポイントは次のとおりです。
| 課題 | 社員の業務範囲が固定化され、スキル獲得の幅が狭まっていた |
|---|---|
| DX推進の内容 | 補助金を活用し、2名の社員がデジタル教育を受けられる環境を作った |
| 結果 | 社員がコア業務を進めながら同時並行でデジタルスキルを学び、スキルが向上した |
同社は生産や加工をメインに行う町工場。社員一人ひとりの業務が固定化されていたことで、個人のスキルに伸び悩みを感じていたといいます。
社員数25名のうち2名が、オンラインによるDX人材育成サービスを利用。その際に「DXリスキリング導入補助金」を活用し、育成コストを抑えたそうです。社員はコア業務を行いながら、勤務時間内にデジタルの基礎や応用を学び、少しずつスキルを向上させていったといいます。
参考:デジタル活用・DX事例集 vol.34 株式会社SND | 東京商工会議所
「自社オリジナルのシステム」を開発すれば、さらにDXの効果を高められる
お伝えしたように、外部のシステムでもDXの効果が期待できますが、「自社オリジナルのシステム」を作ることで、さらにDXの効果を高められます。
独自システムを作るメリットは?
- 「かゆいところに手が届く」システムを開発できる
- 状況に応じて仕様を変えられるので、コストをコントロールしやすい
当社First Creationでは、マーケティングを踏まえたシステム開発を提供しています。自社10名以上のエンジニアに加え、パートナー企業を含めた約350名規模のグローバル開発体制を構築。高いクオリティのシステムを、自社に最適化させた状態で提供します。
無料のメルマガ登録で、DXの成功ノウハウを学べる!
現在当社では、無料のLINEを配信中。DX成功のポイントを惜しげもなくお伝えしています。
学べる内容
- プロダクト開発を成功へ導くためのマインドセット
- 強運の法則
- やる気があるチームの作り方
- エンジニアの採用方法・外注方法
- セキュリティ対策
- プロダクト開発のためのマーケティング戦略
- リーダーのための意識改革ガイド
LINEはいつでも解除でき、無理な営業も一切ありません。自社のDX推進にぜひお役立てください。
【LINE登録はこちらから】
【LINE登録はこちらから】
【まとめ】DXを推進して企業利益の最大化を図ろう
この記事では、DX推進について次のポイントをお伝えしました。
- DXは、デジタル技術の活用によって業務プロセスを効率化すること
- DX推進の目的として「競争力の強化」があげられる
- 代表的な取り組みとして、社内コミュニケーションや書類管理などにツールを用いる方法がある
ぜひ本記事の内容を、自社のDX推進にお役立てください。自社に最適化されたシステムを導入したい場合は、こちらにお問い合わせください。