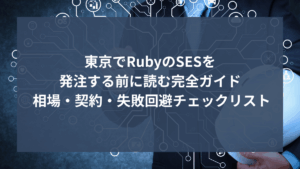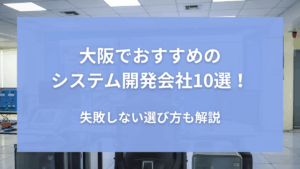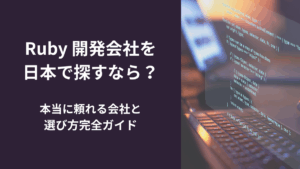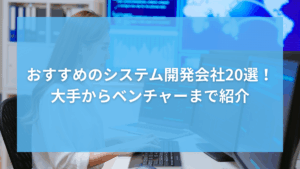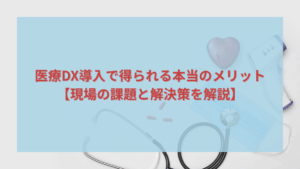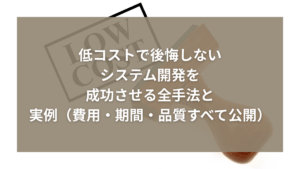「業務負担が大きく、社内でDX化を進めるべきか悩んでいる」
「失敗したくないので、メリットとデメリットの両方をしっかりと把握したい」
最近ビジネスシーンでよく耳にする、DX化という言葉。「何となく”デジタル”や”インターネット”をイメージできるが、詳しくはわからない」といった方もいらっしゃるでしょう。そこで本記事では、企業がDXを進めるメリットを徹底解説します。
DX化にはデメリットもあります。メリットとデメリットの両方を天秤にかけて、自社にとって最適な選択をしましょう。
DX化とは?
DXとは、Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)の略語のことです。わかりやすくいえば、デジタル技術を活用することで、業務プロセスの効率化を図ることを意味します。効率化によって、最終的には組織全体の変革を目指します。
たとえば、会計ソフトによって財務を見える化する、データ分析の結果をマーケティングに役立てる、これらはDXの取り組みのひとつです。
DX化とIT化の違い
「DX化」と「IT化」は、デジタル技術を用いる点において同義ですが、ニュアンスが少し異なります。
| IT化 | 業務効率化や生産性向上、コスト削減が目的 |
|---|---|
| DX化 | ビジネスモデルや組織単位での変化が目的 |
わかりやすくいえば、IT化が狭義、DX化が広義です。デジタル技術を導入して、効率化やコスト削減など、ミクロ的な成果を目指すのがIT化。対して、「デジタル技術によって、企業として大きく変化させたい」と考えるのがDX化です。
DX化によって得られる10のメリット
続いて本題である、DX化のメリットをお伝えします。
- 人手不足でも生産性を確保できる
- 顧客に対してパーソナライズなアプローチができる
- 新たな商品やサービスの開発につながる
- 社内コミュニケーション活性化につながる
- 災害時のリスクヘッジになる
- ペーパーレス化を促進できる
- レガシーシステムを見直す機会になる
- 働き方改革にも対応しやすくなる
- 従業員満足度が高まる
- 企業イメージの向上につながる
1. 人手不足でも生産性を確保できる
DXでは、ソフトウェアやAI-OCR、AI活用など、ITツールを用いるため、生産性向上が期待できます。書類のフォルダ分け共有などもクラウドで行えるため、業務効率の大幅アップが可能です。
社員一人ひとりの生産性が高まれば、採用に力を入れずとも、これまでの人員でも十分に生産性を維持できるでしょう。人手不足に悩まされている中小企業も安心です。
2. 顧客に対してパーソナライズなアプローチができる
データ分析によってパーソナライズなアプローチができるのも、DX化の大きなメリットです。たとえば、CRM(顧客関係管理システム)では顧客のリストや購買履歴を管理できます。解析ツールを用いれば、ホームページやECサイトに対するアクセス数も分析可能です。
誰が何を購入したのか、どういった経路でアクセスしているのかなど、顧客行動を見える化できれば、それに最適化させたアプローチができます。DX化によって、ムダのないマーケティング戦略を行えるでしょう。
3. 新たな商品やサービスの開発につながる
DX化によって蓄積されたデータは、新商品や新サービスの開発にも役立てられます。たとえば、顧客の行動データから潜在ニーズを発見できたり、市場分析の結果から革新的なアイデアが見つかったりします。
また、昨今めまぐるしく進化している「AI」によって機械化を進めれば、より精緻な分析が可能に。いわゆる”当たる商品”を生み出しやすくなるでしょう。
4. 社内コミュニケーション活性化につながる
チャットツールやWeb会議ツールを導入するのもDX戦略のひとつ。これらを導入することで、社内コミュニケーションの活性化につながります。
社内コミュニケーションの定番といえば、電話やメールです。ミーティング時は、1回ごとに会議室を予約し、対面で話し合い、議事録をまとめるといった工程が必要でした。一方で、チャットツールやWeb会議ツールを導入すれば、従来よりもスムーズなコミュニケーションが可能です。
LINEのような感覚で業務連絡ができ、オンライン上で会議の予約から実行までを行えます。最近では「文字起こしツール」も登場しているため、議事録作成の手間もほとんど不要です。
5. 災害時のリスクヘッジになる
DX化を進めることは、BCP(事業継続計画)の強化にもなります。たとえば、クラウド型のシステムを導入すれば、遠隔地のサーバーにデータが保管されるため、災害が起きた場合のデータ消失リスクも低減可能です。
もし書類やデータを、オフィス内の「紙」や「ハードウェア」に保存していた場合、火災が起こると消失してしまうでしょう。クラウドベースに置き換えれば、こうしたリスクを抑制できます。万が一オフィスに出社できない状況でも、仕事をテレワークに置き換えられるため、最低限の事業継続が可能です。
6. ペーパーレス化を促進できる
ペーパーレス化を促進できるのも、DX化の大きなメリットのひとつです。実際に、オフィスに書類が溜まっていく一方で、うまく保管できていない企業も多いはず。企業では取引先や顧客との契約情報、社員の個人情報、などあらゆる情報を扱います。これらを「紙」で管理するのは大きな負担になります。
書類をカテゴリー分けする手間がかかるのはもちろん、保管するスペースも必要です。契約書や顧客台帳などをデジタル化させれば、管理工数を大幅に減らせます。保管スペースが最小限になれば、オフィスも広く感じられるように。さらに働きやすいオフィスを実現できるでしょう。
7. レガシーシステムを見直す機会になる
これまでの業務体制を見直し、「デジタルの力」を使って業務効率を高めていく、これがDXの真骨頂です。DX化に前向きになることは、従来のレガシーシステムを見直すきっかけになります。
レガシーシステムは「単独作業」に特化していて、別の業務と連携できないケースも多いです。その点、最新のクラウドシステムは連携性に優れており、スケーラビリティ(拡張性)に富んでいます。今後の事業展開を見据えて、今からDX化を進めておいて損はないでしょう。
8. 働き方改革にも対応しやすくなる
働き方改革に対応しやすくなるのもDX化の大きなメリット。DXは、リモートワークやフレックスタイムとの親和性が高いです。たとえば、ITシステムを導入することで在宅勤務が可能となれば、従業員のストレス軽減につながります。
オフィスに向かうまでの通勤時間も削減され、ワークライフバランスが向上。企業にとっても、交通費や事務関連費などコストを抑えつつ生産性を維持できます。働き方改革の実現によって、労働者と企業の両方にとって大きなメリットが生まれます。
9. 従業員満足度が高まる
DXでは、組織をあげてデジタル化を進めるため、結果的に従業員満足度が高まります。たとえば、ITシステム導入によるペーパーレス化、リモートワークの推進。さらに社内コミュニケーションの促進など、多くの恩恵を受けられます。
業務効率化や在宅勤務によって、社員が余裕をもって働けるようになるのです。社内の人間関係が良好になり、業務効率も高まる。さらには売上も向上するといった好循環につながる可能性が大いにあります。
10. 企業イメージの向上につながる
DX推進に熱心に取り組むことで、「DX積極的な企業」としてイメージアップが図れます。世間はもちろん、ステークホルダー(顧客や取引先など)からのイメージも重要です。企業の方向性や行動は、株価にも影響を与えます。ネガティブイメージがつけば、株価下落や信頼失墜にもつながってしまうでしょう。
社員や顧客を抱える「企業」である以上、自社のイメージは重要です。DX化に前向きに取り組み、一定の成果を出すことでイメージの向上に努めましょう。
DX化による4つのデメリット
DX化には多くのメリットがある反面、デメリットも存在します。とくに注意しておきたいのは次の4つです。
- デジタルに明るい人材が必要となる
- レガシーシステムからの脱脚が難しい
- 一定のコストや労力がかかる
- 社内全体の協力が不可欠である
1. デジタルに明るい人材が必要となる
DX化によって企業は多くの恩恵を受けられますが、「デジタルに明るい人材がいない」といったケースも少なくありません。そもそもITツールやインターネットなどに明るい社員がいなければ、DX化を進めるのは難しいです。
もし人材がいない場合は、社内にチームを設置して、チームで調べながらデジタルスキルを磨く。あるいは外部に委託するといった方法でDX化を検討する必要があるでしょう。
2. レガシーシステムからの脱脚が難しい
DX化の推進は、レガシーシステムを見直すきっかけになるとお伝えしました。しかし、レガシーシステムから脱却するのは簡単ではありません。多くの企業は「これまでのやり方」をもっていて、社員にも染み付いているはず。今まで当たり前だった体制や仕組みを変えるのは大変です。
社内全体からの同意が必要なうえ、コストと労力をかけてツールを導入し、社員に教育を施したうえ、定着させなければなりません。企業規模が大きかったり、経営年数が増えたりするほどレガシーシステムからの脱却は難しくなります。
3. 一定のコストや労力がかかる
DX推進には一定のコストや労力がかかるので注意が必要です。たとえば、クラウドサービスを導入する場合、初期費用や月額利用料が発生します。利用者数に応じて料金が発生するケースが多く、その場合月間数万円〜数十万円のコストがかかります。
金銭面だけでなく、クラウドサービスを定着させるための教育も必要です。「教える人材」を確保し、社内のITリテラシーを高めなければなりません。ただ単にシステムを導入するだけでなく、定着させるためのコストや労力も踏まえたうえで導入しましょう。
4. 社内全体の協力が不可欠である
DX化の最終的な目標は、デジタル技術によって組織全体の業務体制や経営戦略を変革させること。そのため、導入時は社内からの協力が不可欠です。社長が「DXを推進する!」と掲げたとしても、実際に作業をするのは社員なので、まずは賛同を得なければなりません。
レガシーシステムが浸透している場合、その状態からDXを推進するのは至難の業。経営陣が先頭に立って社内に呼びかけ、まずはスモールスタートさせて成果を出すなどで、社員から信頼を得ることが大切です。
DX化に失敗しないためのコツ
DX導入では一定のコストや労力がかかるので、誰しも「失敗したくない」と思うでしょう。DX化に失敗しないためのコツとして、以下の4つを紹介します。
- まずはスモールスタートさせる
- リーダーが率先して動く
- 目的が曖昧なまま進めない
- システム導入よりも人材育成を優先する
1. まずはスモールスタートさせる
DXは組織全体を変革させるための取り組みです。しかしながら、導入に焦って失敗するケースも少なくありません。社員からの理解を得ないまま、いきなり全社的にDX化を進めれば、当然失敗してしまいます。導入するだけでなく、社員へのデジタル教育にも時間をかけなければなりません。
失敗のリスクを抑えるためには、スモールスタートさせるのがおすすめです。まずは上層部だけ導入してみる、特定の部署やチームだけシステムを使ってみるなど、小さな規模で始めてみてください。
2. リーダーが率先して動く
DX化を進める際は、社長やマネジメント層などリーダーが主体となり、社員を引っ張っていくことが大切です。企業として、DX化で何を成し遂げたいのか、社員にどういったメリットがあるのかなど、社員に対して具体的にメッセージを伝えてください。リーダーが指針を決め、率先して動くことで、少しずつ社員の熱量も増えてくるはずです。
3. 目的が曖昧なまま進めない
DXのよくある失敗例として、「目的が曖昧なことでシステムや施策が定着しない」といったケースがあります。「何となく業務を効率化させたい」など目的が曖昧なままでは、システム効果も測定できません。
まずは、DX化によって社内の課題を解決したいのか、顧客の満足度を高めたいのかを明確にしましょう。その実現のためにどのようなシステムを取り入れる必要があるのか考えることが大切です。
売上拡大の点でいえば、既存のマーケットシェアを増やしたいのか、あるいは新規市場を開拓したいのかなど、方向性を定めることも重要です。
4. システム導入よりも人材育成を優先する
DXの失敗事例として「DX人材がいないのにシステムを先に導入してしまった」といったケースがあげられます。人材がいないのに先走ってシステムを導入し、結果的に定着しなかった、といった例です。まさに「DX自体が目的化」することで、こうした失敗につながります。
そのためシステムを導入する場合は、それを扱える人材や、教育できる人材がいるか確認しましょう。いない場合は、ツールを取り入れる前に、まずは人材育成に注力する必要があります。
DX化に成功した中小企業の事例
続いて、DXを推進したことで業務効率が上がり、組織成長につながった中小企業の事例を紹介します。
【製造業】業務プロセスを見える化 | 株式会社今野製作所
画像引用:株式会社今野製作所
株式会社今野製作所は、自社ブランドの油圧ジャッキをはじめ、板金加工事業を展開する会社です。DXに取り組んだきっかけや内容は次のとおりです。
| 課題(きっかけ) | オーダーメイド受注によって社員の負担が増大していた |
|---|---|
| DX推進の内容 | 「生産管理」と「情報共有」に関するシステムを導入 |
| 結果 | 出荷までのプロセスが可視化され、拠点間のコミュニケーションも円滑になった |
同社は2000年代初期から、イントラネットや電子メールなど「IT」には惜しまず投資してきたそうです。しかしながら、リーマンショックによって業績不振に直面。状況を打開するために、業態を「オーダーメイド受注」に切り替えたものの、社員の負担が大きく、残業時間が増えざるをえない状況になってしまったといいます。
この状況を打破するべく、「生産管理」そして「情報共有」の2軸におけるDX化を推進。受注から調達、製造、出荷まで一連のプロセスを見える化できる「生産管理システム」を導入しました。
情報共有では、ノーコードツールによってオリジナルアプリを作成し、社内外とのやり取りを円滑化。コミュニケーション円滑化によって、業務効率が大幅に高まったそうです。商品の引き合いから出荷までが可視化されたうえ、複数拠点でのやり取りもスムーズになったといいます。
参考:デジタル活用・DX事例集 vol.28 株式会社今野製作所 | 東京商工会議所
【卸売業】DX化によって少数精鋭での安定経営を実現 | 株式会社山秀
画像引用:株式会社山秀
株式会社山秀(さんしゅう)は、ドイツ製ハンガーの正規代理店事業をベースに、家庭用品の輸入雑貨を販売する会社です。DXに関して次のような取り組みを行いました。
| 課題(きっかけ) | 社員一人あたりの業務量が多く、負担に感じていた |
|---|---|
| DX推進の内容 | 自社オリジナルの業務システムを導入した |
| 結果 | 業務負担が軽減、リモートワークへの移行もスムーズにできた |
社員が6名で、一人あたりの業務負担が大きかった同社。「限られた人員でも事業を回せるようにしたい」といった思いがあり、その実現のためにDX化に取り組みました。主に「ホームページのデザイン改良」「ECサイトの構築」「業務システムの導入」の3つに着手したそうです。
業務システムでは、業務負担が大きかった「販売管理」「在庫管理」をテコ入れ。社員の入力負担や確認作業が減るようなシステムを設計し、自社にとって使いやすい仕様にしました。業務負担が軽減したうえ、リモートワークへの移行もスムーズに進んだといいます。
参考:デジタル活用・DX事例集 vol.2 株式会社山秀 | 東京商工会議所
さらに多くの事例を比較したい方は、こちらの記事をご覧ください。
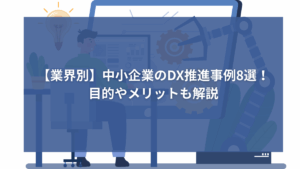
「自社オリジナルのシステム」を開発すれば、さらにDXの効果を高められる
DX化では、新たなITシステムを導入するのが定石です。その際、外部ベンダーのシステムではなく、「自社オリジナルのシステム」を作ることで、さらにDXの効果を高められます。
独自システムを作るメリットは?
- 「かゆいところに手が届く」システムを開発できる
- 状況に応じて仕様を変えられるので、コストをコントロールしやすい
当社First Creationでは、マーケティングを踏まえたシステム開発を提供しています。自社10名以上のエンジニアに加え、パートナー企業を含めた約350名規模のグローバル開発体制を構築。高いクオリティのシステムを、自社に最適化させた状態で提供します。
無料のLINE登録で、DXの成功ノウハウを学べる!
現在当社では、無料のLINEを配信中。DX成功のポイントを惜しげもなくお伝えしています。
学べる内容
- プロダクト開発を成功へ導くためのマインドセット
- 強運の法則
- やる気があるチームの作り方
- エンジニアの採用方法・外注方法
- セキュリティ対策
- プロダクト開発のためのマーケティング戦略
- リーダーのための意識改革ガイド
LINEはいつでも解除でき、無理な営業も一切ありません。自社のDX推進にぜひお役立てください。
【今すぐにプレゼントを受け取る】
【今すぐにプレゼントを受け取る】
【まとめ】DX化は企業に多くの利益をもたらしてくれる
DX化は中小企業に多くのメリットをもたらしてくれる素晴らしい取り組みです。しかしながら、導入すれば必ず効果が出るものではありません。成功のためには、デジタルに明るい人材が必要であり、社員の賛同や協力も不可欠です。失敗を避けるためにも、目的を明確にし、スモールスタートさせることをおすすめします。
DXを推進するにあたって、自社に最適化されたシステムを導入したい場合は、こちらにお問い合わせください。